支部主催の講演会:過去の記録
「蛋白質の折り畳みダイナミクスにおける
ポリペプチド鎖の不均一性」
日時:2006年12月1日(金)17:00〜
場所:理学部5号館2階5-2-05号室
講師:木村 哲就 博士
所属:日本学術振興会特別研究員・カリフォルニア工科大学
講演概要
蛋白質の立体構造形成(折り畳み)反応には多数の経路が存在することが理論的に提案されている.しかし、ポリペプチド鎖の不均一性を実験的に求めることが困難なため,折り畳み経路についての詳細な検証はほとんどできていない.本講演では,レーザー分光測定を用いて明らかにした蛋白質の不均一性と折り畳みダイナミクスについて報告し,折り畳み機構について理論・実験の両面から議論したい.
ご案内のダウンロード
連絡先: 北海道大学大学院理学研究院 化学部門
物理化学分野 構造化学研究室
石森浩一郎 koichiro(at)sci.hokudai.ac.jp
TEL:011-706-2707
「メカニカルストレスの基礎と臨床応用」
日時: 平成18年12月7日(木) 17時30分~19時00分
場所: 旭川医科大学・機器センター3F・カンファレンスルーム
講師: 成瀬 恵治 教授
(岡山大学・院・医歯薬総合研究科)
講演要旨:
我々の体は常に外界から様々なメカニカルストレスを受けている。特に循環器系組織は血行動態から常にメカニカルストレスを受け、細胞内情報に変換し適応している。このメカノ受容体→細胞内情報伝達機構→細胞応答までを含めたメカノトランスダクション機構を半導体製造技術を応用したソフトリソグラフィー(Soft Lithography)法を駆使し通常の細胞生物学的・分子細胞学的アプローチのみではなしえなかった研究を行うことが可能となった。さらにその応用としてマイクロ流路良好運動精子分離システム、またストレッチ刺激負荷受精卵共培養システムなどを用いた不妊症治療システムを開発し臨床治験を行い良好な結果を得ている。
本講演ではこのソフトリソグラフィーを用いた基礎医学的研究(①細胞ストレッチ刺激チャンバーを用いた機械受容チャネルの分子生理学的研究、②マイクロ・コンタクトプリンティング法を用いた細胞形態制御、③マイクロチャネルを用いた流体力学的研究)とその臨床応用(生殖補助医療、再生医療)について講演する。
ご案内のダウンロード(word形式)
なお、本講演会は、旭川医科大学の「最新医学フォーラム」および「大学院最新医学特論」を兼ねて開催し、また「日本医師会生涯教育講座」(5単位)として、北海道医師会の認定を得ております。
連絡先: 旭川医科大学生理学講座・自律機能分野
高井 章
TEL:0166-68-2320
E-Mail:takai(at)asahikawa-med.ac.jp
"Spectroscopic Studies of Bacterial Heme Transport Proteins"
日時:2006年11月 2日(木)16:00〜
場所:理学部5号館2階5-2-05号室
講師:Professor Kenton R. Rodgers
所属:North Dakota State University
講演概要:
多くの病原菌は生存に必要な鉄の供給源として宿主のヘムに依存しているが,生体内の遊離のヘム濃度はその細胞毒性から非常に低く,多くの場合,蛋白質などと結合している.したがって,病原菌はヘムを取り込みと輸送のための巧妙な機構を有しているが,本講演ではこのような分子機構について,分光学,特に共鳴ラマン散乱スペクトルを用いた研究を紹介する.
ご案内のダウンロード(word形式)
標記講演会は大学院理学院化学専攻『魅力ある大学院イニシアティブ「高邁なる大志を抱いたT 型化学者養成」プログラム』の支援を受け、「化学研究総合講義Ⅱ」の一部として認定されております.
「魅力ある大学院教育」イニシアティブ
高邁なる大志を抱いたT型化学者養成
T-type Chemists with Lofty
連絡先:北海道大学大学院理学研究院 化学部門
物理化学分野 構造化学研究室
石森 浩一郎 (TEL:011-706-2707)
「イオンポンプと光センサーの機能を決めるもの:
相互機能変換からわかること、わからないこと」
日時:2006年11月1日(火)15:00〜
場所:理学部2号館5階 2-507号室
講師:須藤 雄気 博士研究員
所属:テキサス大学ヒューストン校
講演概要:
生物は、光をエネルギー源、もしくは情報伝達源として利用する。
最近我々は、光エネルギー変換を司る蛋白質と、光情報変換を司る蛋白質と間で相互機能変換を実現することに成功した1),2)。講演ではこれまでの知見と併せ、機能変換から「わかっ たこと」、「わからなかったこと」について議論する。
[1] Sudo, Y., et al. (2006) JBC
[2] Sudo, Y., and Spudich, J.L. (2006) PNAS
ご案内のダウンロード(word形式)
連絡先:北海道大学大学院先端生命科学研究院
先端生命科学部門 生物情報解析科学研究室
出村 誠 (TEL:011-706-2771)
「金属酵素における酵素活性制御因子;
分光学的に活性部位をみる」
日時:2006年9月19日(火)16:00〜
場所:理学部5号館3階5-3-04号室
講師:当舎 武彦 博士
所属:日本学術振興会特別研究員・岡崎統合バイオサイエンスセンター
講演概要
生体内において種々の化学反応を行っている金属酵素は、非常に類似した活性中心構造をもつにもかかわらず、異なる化学反応を触媒する例がよくみられる。本講演では、金属酵素が固有の酵素活性を持つに至る制御因子を解明するために、分光学やアミノ酸置換体を利用して行った研究について、最新の例を報告したい。
ご案内のダウンロード(word形式)
連絡先:北海道大学大学院理学研究院 化学部門
物理化学分野 構造化学研究室
石森浩一郎 (TEL:011-706-2707)
日時:平成18年7月28日(木)13時30分~16時30分
場所:室蘭工業大学・共同利用施設・S201号室
13時30分~
「視物質の色変化から色識別へ – 半世紀の歩み」
講 師: 吉澤 透 先生
(京都大学名誉教授・日本生物物理学会名誉会員)
講演要旨:
目の網膜の中には、光に感じるロドプシンというタンパク質(明暗を見分ける視物質)がある。このタンパク質の光反応は視興奮過程の最初に起こる反応であるので、その解明は、視覚の分子機構の解明の最重要課題であると考えられていた。
演者は、大阪大学院生の時、液体空気及び窒素を用いて、世界に先駆けて低温実験を行い、赤紫色の新光産物を発見し、Natureに報告した(1958)。この論文の縁で、3年間Harvard大のWald教授に招待され、この光産物の吸収極大は543nmにある事を確かめた。さらに「ロドプシンから赤紫色中間体への変化はロドプシンの発色団レチナールの11-シス型から歪んだトランス型への光異性化反応である」ことを提唱した。
帰国後、液体ヘリウム温度で、また京都大学に赴任してからはピコ秒レーザー装置を組み立て、第一光産物を分光学的に追求し、赤紫色の中間体(バソ)より先に青色のホト中間体(560nm)が常温で25ピコ秒以内に生じることを見いだした。この産物が第一光産物で、現在はフェムト秒レーザーで研究されている。
定年少し前から、ニワトリの視物質について本格的に研究を始めた。4種の色覚視物質の抽出に成功し、分子進化的研究を行い、「色覚視物質はロドプシンより先に進化してきた」という学説を発表した。
ご案内のダウンロード(word形式)
15時00分~
「Proteomic Trajectory Mapping of Biological Transformation」
講 師: Dr. Hiroyuki Matsumoto
University of Oklahoma Health Sciences Center
Professor of Biochemistry and Molecular Biology
講演要旨
本講演では、誕生後の未熟網膜が成熟する過程を、演者のグループで確立したProteomic Trajectory Mappingと云う手法で研究した結果を紹介する。Proteomic Trajectory Mappingでは、網膜の成熟過程を2次元ゲルで追跡し、成長過程の時間変化をすべてのタンパク質とその量の発現の時間依存性(Proteomic Trajectory)として記載する。さらに、得られたProteomic TrajectoriesをSelf-Organizing Maps (SOM)によっていくつかのグループに分類した。Proteomic Trajectory Mapping で得られたデータを、Bioinformaticsを駆使して如何に解釈し、生物系の変化の理解に役立てることが出来るかを議論する。さらに、Proteomic Trajectory Mapping が生物系の生理的な(正常な)変化や病理的な変化を研究するうえで非常に重要な概念となるであろうことを予言し、また薬物の治療効果をモニターするためにも役に立つことを示唆する。
ご案内のダウンロード(word形式)
連絡先:
室蘭工業大学 材料物性工学科
岩佐 達郎
TEL:0143-46-5661
「蛋白質の立体構造形成の一般則を探る」
日時:2006年6月12日(月)16:00〜
場所:理学部5号館2階5-2-05号室
講師:鵜澤 尊規 博士
所属:日本学術振興会特別研究員 京都大学大学院工学研究科
講演概要:
タンパク質はそのペプチド鎖がとりうる無数の構造からどのようにして唯一の安定な立体構造を選び出すのであろうか.本講演では独自の技術により開発した高時間分解能の高速混合装置とNMR測定におけるH-D交換法を組み合わせることで,タンパク質の立体構造構築における基本原理の解明にどこまで迫れるのか,またそこには一般則が存在するのかどうか議論したい.
ご案内のダウンロード(word形式)
連絡先:
北海道大学大学院理学研究院 化学部門
物理化学分野 構造化学研究室
石森浩一郎
TEL:011-706-2707
「生体分子複合体の固体NMRによる構造解析」
日時:2006年6月5日(月)16:00〜
場所:理学部2号館4階404号室
講師:藤原 敏道 先生
所属:大阪大学蛋白質研究所 構造生物学研究部門
講演概要:
脂質二重膜にある蛋白質やアミロイドなど線維状蛋白質は、結晶化が難しく可溶化すると本来の構造や機能がなくなることがしばしばある。固体NMRは、このような大きな生体分子複合体の構造解析ができる。講演では、固体NMRによる膜に結合したペプチドや膜蛋白質、巨大な集光アンテナ複合体などの構造解析、構造決定法を紹介する。
ご案内のダウンロード(word形式)
連絡先:
北海道大学大学院理学院 生命理学専攻
生命解析学講座 分子生命科学研究室
(高分子第5研究室) 河野 敬一
TEL:内線2770
「タンパク質によるDNA上のスライディングにおける
thermal fluctuationのマクロ的意義」
日 時: 平成18年5月11日(木) 15時00分より
場 所: 北海道大学 理学部2号館5階505号室
講 師: 国立遺伝学研究所 構造遺伝学研究センター
嶋本 伸雄 教授
要 旨:
DNA結合タンパク質の多くは、DNAの特定の位置(specific site)に結合したspecific complexの形で機能し、specific
site への結合時に特定の位置以外のDNA(nonspecific sites)上を1次元的拡散(スライディング)する。スライディングはspecific
siteへの結合を加速する効果を持つと期待できるが、一般にタンパク質の機能において、specific siteへの結合は十分早く、律速過程でないので、結合平衡定数(affinity)が変わらない限り、結合の加速は生理的には意味がない。しかし、現実には、スライディングできる部分が長ければ長いほど、specific
siteへの結合平衡定数 (affinity)が大きくなるDNA結合タンパク質が存在し、E. coli TrpRでは細胞内でもその機構は機能していた。一見、熱力学に矛盾するこの効果の分子機構は、P.
putida CamRの1分子ダイナミクスによって明らかになった。つまり、specific siteへの結合は、スライディングによって加速されるが、そこからの解離は、スライディングを介さず起こり、スライディング出来る部分の長さに独立であった。この現象の理解は、chemical
kineticsとthermodynamicsがどうstatistical mechanicsから基礎付けられているかに係わる深さを持つ問題である。
要旨のダウンロード(Word形式)
問合せ先:
北海道大学 大学院理学院 生命理学専攻 川端 和重
TEL: 011-706-2769
「膜タンパク質モデリングと
インシリコスクリーニングへの展開」
ポスター(PDF形式)
日 時: 2006年4月17日(月) 17時~18時
会 場: 北海道大学理学部2号館5階507室
講 師: 産業技術総合研究所 生命情報科学研究センター 広川貴次 先生
要 旨:
バイオインフォマティクス技術によるタンパク質のモデリングと創薬への展開を、代表的な創薬標的タンパク質であるGタンパク質共役型受容体を例に紹介する。具体的には、ヒスタミンH1受容体を実施例としてモデリングからリガンドドッキング計算のための戦略とインシリコスクリーニング結果、問題点など議論する予定である。
参 加: 自由(会員以外の方もせびご参加ください)
問合せ先:
北海道大学・大学院先端生命科学研究院 出村 誠
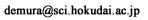
TEL: 011-706-2771
「生体ナノ力学とその細胞レベルへの応用」
日 時:2006年1月12日(木)15:30~
場 所:北海道大学理学部2号館5階505号室
講 師:猪飼 篤 教授 (東京工業大学大学院生命理工学研究科)
原子間力顕微鏡の使用によりタンパク質などの生体高分子や生細胞に直接触ってその映像をとり、その硬さを測定できるようになった。酵素はランダムコイルのように柔らかくても、また岩のように硬くてもその機能を果たせないが、原子間力顕微鏡の使用により、機能発現に必要な硬さを定量的に論じることが可能となりつつある。また、細胞を生かしたままの状態でその膜タンパク質やmRNAを回収して単一生細胞プロテオミクス研究を可能とする方法も開発されつつある。これらの操作をより身近なものとするには生体高分子間の非共有結合性相互作用を定量的に理解し、人為的に制御するソフトナノテクノロジーの方法論が有用である。
連絡先:大学院理学研究科生物科学専攻
川端 和重(内線2769)
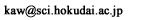
|