#19-2 2019年「第59回生物物理若手の会夏の学校」会期: 8月26日-8月29日 場所: 兵庫県神戸市 神戸セミナーハウス 世話人: 大阪大学蛋白質研究所 荒谷剛史 詳細はこちらへ ポスター ダウンロード #19-1
|
| 2010年度 |
#13-1
「瞳関数制御による新しいレーザー顕微鏡の展望」
日時: 2013年8月22日(水)15時00分~17時00分
場所: 北海道大学 創成科学研究棟 5階 大会議室
講演要旨(ダウンロード)
15:00 挨拶・「瞳関数制御顕微鏡の概要」
浜松医科大学 常葉大学
名誉教授 寺川 進
15:20 「瞳関数制御顕微鏡のための空間光変調器について」
浜松ホトニクス株式会社・中央研究所
主任部員 井上 卓
15:45 「瞳関数制御顕微鏡の現状」
浜松医科大学メディカルフォトニクス研究センター
特任教授 岡崎 茂俊
16:10 「瞳関数制御顕微鏡のためのマルチスポット用CMOSセンサーの開発」
静岡大学 電子工学研究所
教授 川人 祥二
16:35 「瞳関数制御を用いたホログラフィック多点FCSの開発」
北海道大学先端生命科学研究院
特任助教 山本 条太郎
JST先端計測H21年度採択課題「瞳関数制御による高度多機能光学顕微鏡の開発」研究会
後援: 日本生物物理学会 北海道支部会
問い合わせ先:
北海道大学 先端生命科学研究院 細胞機能科学分野
山本 条太郎
email: jyamamoto [at] sci.hokudai.ac.jp、TEL:011-706-9542
| 2010年度 |
#10-4
"Coherent X-ray Diffraction Imaging (CXDI) for the Study of Nano-scale Materials and Devices"
日時: 2010年9月8日(水)13時30分~ (30分程度)
場所: 北海道大学 電子科学研究所 1階 会議室
講師: Dr. Marcus C. Newton
(Advanced Technology Institute, University of Surrey, UK)
講演要旨(ダウンロード)
Selected Papers by Dr. M. C. Newton:
[1] Newton M.C., Henley S.J., Friar J., Silva S.R.P.,
"In-situ Plasma Assisted Doping of ZnO Nanostructures",
Nature Nanotechnology, in press (2010)
[2] Newton M.C., Leake S.J., Harder R. and Robinson I.K.,
"Three-Dimensional Imaging of Strain in a Single ZnO Nanorod",
Nature Materials 9, 120 (2009)
[3] Newton M.C. and Warburton P.A.,
"ZnO tetrapod nanocrystals",
Materials Today 10 (5), 50 (2007).
主催: 北海道大学 電子科学研究所 コヒーレントX線光学研究分野
共催: 北海道大学 ビームライン研究会
問い合わせ先:
北海道大学 電子科学研究所 コヒーレントX線光学研究分野
西野吉則、yoshinori.nishino(at mark)es.hokudai.ac.jp、内線:9354
#10-1
グローバルCOE物質科学イノベーション講演会主催
「哺乳類における胎生、ゲノムインプリンティングの獲得とレトロトランスポゾンの寄与について」
日時: 平成22年5月11日(火) 13時00分~
場所: 北海道大学理学部7号館 219/220室
講師: 石野 史敏 先生
東京医科歯科大学難治疾患研究所・エピジェネティクス分野 教授
講演要旨:
哺乳類の進化の中で、どのように胎生の獲得は起きたのであろうか?私たちは哺乳類特的なエピジェネティック機構であるゲノムインプリンティングの解析から、Peg10とPeg11/Rtl1という2つの父親性発現インプリント遺伝子が、胎盤の形成と機能に重要な働きをしていることを明らかにした。どちらもLTR型レトロトランスポゾンが哺乳類の祖先ゲノムに挿入され、その後、内在遺伝子化したものである。ゲノムインプリンティングの片親性発現調節に重要な配列自身も、ゲノムに新規挿入されたDNAに由来する。哺乳類の特徴的なゲノム機能の獲得と成立には、レトロトランスポゾンが大きく寄与していることが明らかになってきた
ご案内のダウンロード
連絡先:
北海道大学大学院理学研究院化学部門
村上 洋太
Tel:011-706-3813
E-mail: yota(atmark)sci.hokudai.ac.jp
| 2009年度 |
#09-10
産総研 ゲノムファクトリー研究部門主催
「異分野ネットワークで可能性を切り拓こう- 将来の融合研究を見据えて -」
日時: 平成22年2月19日(金) 16時30分~
場所: 産総研 北海道センター大講堂 (A棟2階)
参加無料(懇親会:4,000円)
<参加申込み>
E-mailまたはFAXにて以下の内容を2月16日までに事務局までお送り下さい。
1)氏名 2)勤務先 3)役職 4)E-mail または FAX番号 5)懇親会参加有無
連絡先:
産総研 ゲノムファクトリー研究部門 講演会事務局
〒062-8517 北海道札幌市豊平区月寒東2条17丁目2-1
http://unit.aist.go.jp/rigb/
E-mail: 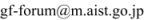
Fax : 011-857-8915
<プログラム>
12:30 - 受付開始
13:00 - 13:10 開会挨拶
ゲノムファクトリー研究部門 研究部門長 鎌形 洋一
13:10 - 13:45 「ノンエンベロープウイルス粒子放出の分子機構」
国立感染症研究所 鈴木 忠樹 先生
13:45 - 14:20 「新たなアプローチからのエピジェネティクスの解明」
福井大学 沖 昌也 准教授
14:20 - 14:55 「遺伝子組換えイネを用いた物質生産について」
日本製紙株式会社 笠原 さおり 主任研究員
14:55 - 15:10 休憩
15:10 - 15:45 「ユニークな装置から出てくる楽しい結果」
日本電子株式会社 寺本 華奈江 先生
15:45 - 16:20 「産業展開を指向した蛋白質相互作用解析」
東京大学大学院 津本 浩平 准教授
16:20 - 16:55 「遺伝情報の拡張を目指した人工塩基対の開発」
理化学研究所チームリーダー/タグシクス・バイオ株式会社代表取締役
平尾 一郎 先生
16:55 - 17:30 「フェロセンを利用したバイオセンシングシステムの開発」
九州工業大学大学院 バイオマイクロセンシング技術研究センターセンター長
竹中 繁織 教授
17:30 - 17:40 閉会挨拶
ゲノムファクトリー研究部門 副研究部門長 湯本 勳
18:30 - 懇親会
-------------------------------------------------------
○専門分野外の方にも分かり易くご説明頂きます。
○ご関心のある方は是非ご参加ください。
○お問い合わせ、ご意見だけでも大歓迎いたします。
#09-9
「北大細胞生物研究集会」との共催
「平成21年度 北大細胞生物研究集会」
日時: 平成22年3月9日(火) 10時00分~(開始時刻は予定です。)
場所: 北海道大学 (会場は参加人数が確定次第、ご案内いたします。)
【懇親会】講演会終了後、ささやかな懇親会を予定しています。
会費は当日受付にて承ります(学生1,000円、学生以外2,000円)。
【発表形式】液晶プロジェクターをご用意します。発表はご自身のパソコンを
ご使用下さい。発表時間:20分(発表10分、質疑応答10分)
【参加登録】
[締め切り] 2月26日(金)17:00
[参加申込] 氏名
所属
懇親会の出欠
連絡先e-mailアドレス
を下記宛先までお送り下さい。
[宛先] 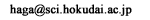
【講演申込】
[締め切り] 2月26日(金)17:00
[発表申込] 講演題目
氏名(発表者氏名の前に○)
所属
連絡先e-mailアドレス
を下記宛先までお送り下さい。参加登録を併せてお済ませ下さい。
[要旨提出] 図表を含めてA4で1ページの要旨を作成し、
Word、あるいはPDF形式のファイルでe-mail添付にてお送り下さい。
[宛先] 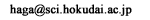
#09-5
「日本生化学会北海道支部会」との共催
「細胞質分裂のメカニズム~酵母や動物細胞はどのようにして分裂するか」
日時: 平成21年10月1日(木) 16時30分~
場所: 北海道大学理学部7号館 219/220室
講師: 馬渕 一誠 先生
学習院大学大学院自然科学研究科 教授
講演要旨:
細胞の分裂は生物の発生、成長に必須である。では細胞はどのようにして分裂するのだろうか。原始的な細胞である酵母や動物細胞はアクチンフィラメントとミオシンからなる『収縮環』と呼ばれる構造の収縮によって分裂する。収縮環の基本成分はこのように筋肉に似ている。しかし収縮環は細胞質分裂の時にしか形成されない点や100%収縮してしまう点が筋肉とは決定的に異なる。収縮環の構造、その形成の過程、分裂位置の決定などについて述べる。
ご案内のダウンロード
連絡先:
北海道大学大学院理学研究院化学部門
高橋 正行
Tel:011-706-3814
![]()
#09-4
シンポジウム
「2nd Symposium on Structural Analysis of Biological Macromolecules & 7th Japan-Korea Bilateral Symposium on Biological NMR」
日時: 7月27日(土)~7月28日(火)
場所: 北海道大学 シオノギ創薬イノベーションセンター1F
主催: 組織的な大学院教育改革推進プログラム
「融合生命科学プロフェッショナルの育成」(FB-station)
ポスター、プログラム、会場アクセスにつきましては、下記URLをご参照ください。
http://altair.sci.hokudai.ac.jp/grad/fb_station/archives/491
ポスターのダウンロード
連絡先:
北海道大学大学院理学研究院
生命理学部門分子生命科学研究室
河野 敬一
Tel:011-706-2770
#09-3
シンポジウム
「International Symposium on Photonic Bioimaging」
日時: 8月1日(土)~8月4日(火)
場所: 京王プラザホテル札幌
会費: 一般2000円、学生1000円
Speakers
* Feng Zhang (Stanford University, USA)
Circuit-breakers: Optical Technologies for Probing Neural Signals and Systems
* Takeharu Nagai (Hokkaido University)
Deciphering Enigma of Biological Function by Genetically-encoded Molecular Spies
* Jonas Ries (Biotech, Germany)
Fluorescence Correlation Spectroscopy in Developmental Biology
* Masataka Kinjo (Hokkaido University)
Membrane-biding Proteins Analyzed by Multi-point Total Internal Reflection Fluorescence Correlation Spectroscopy
詳しい情報は下記のサイトをご覧下さい。
http://www.ec-pro.co.jp/sapporosymposium/index.html
ポスターのダウンロード
連絡先:
北海道大学大学院 医学研究科 先端的光イメージング研究拠点
榎木亮介 (内線:4780)
#09-2
「COMPUTER-BASED ANALYSIS OF BACTERIAL CHEMOTAXIS」
日時: 2009年7月14日(火) 10:30~12:00
場所: 北海道大学・理学部2号館 409号室
講師: Dr. Dennis Bray (University of Cambridge, UK)
講演要旨:
• Bacteria such as E.coli can detect and swim towards distant sources of food and away from poisons. Proteins responsible for this chemotaxis response have been identified, biochemically characterized and their atomic structure determined. It is one of the best-understood forms of biological behaviour.
• E. coli chemotaxis is an excellent system for computer simulations. Programs based on ordinary differential equations (ODEs) allow the concentrations of signalling intermediates to be calculated and the swimming of both wild type and mutant bacteria predicted. Programs linked to graphical displays can test the response of bacteria of any specified genotype to precisely defined stable gradients of any required shape (including those that are difficult, or impossible, to achieve in the real world)
• Not all data can be easily fit by ODE simulations. As experimental approaches become more quantitative and closer to the molecular details, so more sophisticated methods of computation become necessary. We have developed stochastic programs to represent individual protein molecules, in the correct location in the cell and chemical state. These allow the diffusion of molecules in the cytoplasm to be analysed and help us unravel the complicated molecular events of signal processing.
For more information please see: www.pdn.cam.ac.uk/comp-cell
プログラムのダウンロード
連絡先:
北海道大学電子科学研究所
中垣 俊之
Tel:011-706-9432
2008年度 |
#08-6
共催シンポジウム
「自然免疫の認識分子から抗菌ペプチドまで」
日時:
10/28(火) 9:30~18:05
10/29(水) 10:00~11:55
場所:
北海道大学 シオノギ創薬イノベーションセンター1階
産学コミュニティーホール(札幌市北区北21条西11丁目)
プログラムのダウンロード
連絡先:
北海道大学大学院理学研究院
生命理学部門分子生命科学研究室
河野 敬一
Tel:011-706-2770
#08-5
「北海道大学大学院工学研究科応用物理学専攻」との共催
「コヒーレントX線で切り開く構造可視化の新手法」
日時: 2008年10月28日(火) 16:30~17:30
場所: 北海道大学工学部・工学研究科 B11(正面玄関入って左側の講義室)
講師: 西野 吉則 氏 (理化学研究所・専任研究員)
講演要旨:
X線は、1985年にレントゲンによって発見されて以来、構造可視化に広く使われている。 マクロな世界では、X線写真やX線CTは、厚い物体の内部を透視する技術として、病院での臨床診断や空港での手荷物検査など、身近なところで使われている。一方、原子の世界では、X線回折を利用した結晶構造解析は、原子構造決定の有力な手法として確立している。
このようにX線は、マクロな世界から原子の世界までを見ることのできる優れた特徴を持っているが、高空間分解能での構造決定はこれまで、試料が結晶である場合に限られていた。結晶以外の試料に対しても高空間分解能での構造可視化を可能にする手法として、近年になって、X線回折顕微法が実現した。X線回折顕微法では、波としての位相の
揃ったX線(コヒーレントX線)による試料の回折パターンから、試料構造を再構成する。この新手法を使った、細胞の高空間分解能可視化や、医療分野で重要な膜タンパク質の構造解析など、様々な応用の可能性が世界的に盛んに議論されている。
歴史的に見て、X線を使った構造可視化手法は、新しいX線源の出現とともに発展してきた。現在、日米欧の三拠点で、次世代のX線源であるX線自由電子レーザーの建設が進められている。X線自由電子レーザーを用いて、これまで見ることのできなかった世界に光がともされることが大いに期待される。講演では、X線を用いた構造可視化手法の、過去、現在、未来についてお話をしたい。
連絡先:
北海道大学大学院工学研究科
応用物理学専攻 生物物理工学研究室
郷原 一寿
Tel: 011-706-6636
2007年度 |
#07-9
「日本生化学会北海道支部会」との共催
「ホモポリペプチドのβシ-ト形成 -神代の頃の研究-」
日時: 平成19年10月25日(木) 16時00分~18時00分
場所: 北海道大学理学部5号館5-302室
講師: 前田 悠 名誉教授
九州大学 (現福岡大学非常勤講師)
講演要旨:
蛋白質は一次構造(アミノ酸配列)により特徴づけられるが、同時にすべての蛋白質はポリペプチドという共通の化学構造を持っている。従って、蛋白質の示す性質には必ずこの二つの寄与(個性と共通項)が含まれることになる。二次構造やmotifは共通項の象徴であり、二次構造の代表的なものとしてα-ヘリックス(α-helix)とβ構造(β-sheet)がある。α-ヘリックスは一次元系であり、基本的なことは1960年代の終わりには明らかにされていた。しかし、もう一つの二次構造であるβ構造については、その二次元性に由来する困難のために展開が遅れていた。これは「分子間相互作用と分子内相互作用の競合」という高分子に共通の難問の一例である。蛋白質中のβシ-トの構成(トポロジー)が多種多様であることは一次構造上の任意の部分の残基の間で水素結合を形成できるというβシ-トの特徴に由来している。また、βシ-トは会合し易く、会合が不可逆のことが多い。
本講演では、ホモポリペプチド(単色の紐)のβシ-ト形成について得られている知識を紹介して、それを蛋白質(まだらの紐)の立体構造形成の研究に役立て頂くことを願っている。
ご案内のダウンロード
連絡先:
北海道大学大学院理学研究院
生命理学部門分子生命科学研究室
河野 敬一
Tel:011-706-2770
![]()
2006年度 |
"Application of dynamic solid-state NMR to solid proteins"
日時:5月11日(木)午後4時30分より
場所:工学部物理工学系会議室 A1 – 17 室(A棟北側)
講師:Detlef Reichert 博士
(Martin-Luther Universitaet Halle-Wittenberg, Dep. of Physics, Halle, Germany)
後援:日本生物物理学会北海道支部
担当:
平沖敏文(北大・院工・応用物理学専攻 ソフトマター工学研究室)
2005年度以前 |
"Myosin heavy chain isoforms in the renal microcirculation:
Relationship
to contractile kinetics and function"
主催: 日本生化学会北海道支部
共催: 日本生物物理学会北海道支部
日時: 2005年3月17日(水)
場所:
北海道大学理学部7号館(旧化学第二棟)二階7-2-19-20演習室
演 者: Professor Michael P. Walsh
Smooth
Muscle Research Group, University of Calgary Faculty of
Medicine, Calgary,
Alberta, Canada
Canada Research Chair (Tier I) in Biochemistry
Director,
CIHR Group in Regulation of Vascular Contractility
「脳を知り、脳を育む」
主催:北海道歯学会 第241回例会
共催:日本薬学会北海道支部・日本動物学会北海道支部・日本生物物理学会北海道支部
日時:2004年年7月12日月曜日
場所:北海道大学歯学部 講堂
演者:東北大学未来科学技術共同研究センター教授 川島 隆太 先生
鈴木
範男(北海道分子生物学研究会会長、北大院理学研究科)
「味覚の受容・情報伝達機構」
主催:北海道歯学会
日本薬学会北海道支部・日本生物物理学会北海道支部・日本動物学会北海道支部
日時:2003年10月30日(木曜日)
場所:北海道大学歯学部 講堂
演者:九州大学大学院歯学研究院 二ノ宮 裕三 先生